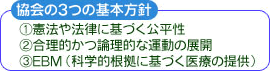個別指導対策講習会(2013年7月28日開催)
実践すべき対策を学ぶ。帯同弁護士からも報告
個別指導対策講習会をラフレさいたまにて、7月28日に開催。医師、歯科医師、スタッフ等あわせて102人が参加した。オリジナル冊子「個別指導対策の要点」をテキストに、協会講師陣が「個別指導の現状」、「関連法規」、「カルテ記載」について解説した。
●「知らなかった」では許されない
冒頭の挨拶で小橋審査指導対策部部長は、個別指導対策のポイントとして、不正、不当な医療は行わないこと、医療に関する法規類を熟知すること、カルテ記載を充実させることを挙げた。不正、不当な行為は絶対に許されず、「知らなかった」との主張は認められないため、本講習会で知識を得ていただきたいと注意喚起した。
冒頭の挨拶で小橋審査指導対策部部長は、個別指導対策のポイントとして、不正、不当な医療は行わないこと、医療に関する法規類を熟知すること、カルテ記載を充実させることを挙げた。不正、不当な行為は絶対に許されず、「知らなかった」との主張は認められないため、本講習会で知識を得ていただきたいと注意喚起した。
●保険医を守る「弁護士の帯同」
「個別指導の実際」では本内審査指導対策部員が講師を務めた。
協会には九五年から150件以上の個別指導に弁護士が帯同した実績があり、不安があれば協会顧問弁護士が帯同することや、帯同することで厚生局の心証を悪くすることはなく、今は全国的に行われていることを強調した。また、高点数の医療機関が一定サイクルで集団的個別指導や個別指導に選定される仕組みを解説するとともに、その問題点を指摘した。
「個別指導の実際」では本内審査指導対策部員が講師を務めた。
協会には九五年から150件以上の個別指導に弁護士が帯同した実績があり、不安があれば協会顧問弁護士が帯同することや、帯同することで厚生局の心証を悪くすることはなく、今は全国的に行われていることを強調した。また、高点数の医療機関が一定サイクルで集団的個別指導や個別指導に選定される仕組みを解説するとともに、その問題点を指摘した。
 |
| 協会顧問弁護士の神田雅道氏 |
続いて、保険診療に関連する法規類について、渡辺審査指導対策部員が講師を務めた。法規類を理解していれば、逸脱した指摘にも毅然と対応できると強調し、療養担当規則、健康保険法、行政手続法、指導大綱、個人情報の保護やカルテの電子媒体への保存に関する法律などの要点を整理して解説した。
●自主返還には安易に同意しない
今年度の講習会では、数々の個別指導に帯同している、協会顧問の神田弁護士が、「弁護士から見た個別指導」と題して報告した。個別指導の後に指導結果とともに「返還項目」が通知されるが、高点数等個別指導では千万単位の額になってしまうこともある。返還することに法的な義務はないため、指導当日の指摘に対して安易に同意せず、「後日検討する」などと対応した方がよいと呼びかけた。
今年度の講習会では、数々の個別指導に帯同している、協会顧問の神田弁護士が、「弁護士から見た個別指導」と題して報告した。個別指導の後に指導結果とともに「返還項目」が通知されるが、高点数等個別指導では千万単位の額になってしまうこともある。返還することに法的な義務はないため、指導当日の指摘に対して安易に同意せず、「後日検討する」などと対応した方がよいと呼びかけた。
●カルテ記載を医科、歯科ごとに講習
カルテ記載については、医科歯科それぞれで講習。
医科では小林審査指導対策部員が講師を務めた。カルテの様式および記載の方法、診療報酬の算定要件等で注意が必要な点について説明した。特に医学管理、在宅医療の算定要件の多くに「管理・指導内容の要点を診療録に記載すること」との規定があるため、カルテ記載が特に重要であると強調した。
歯科では金子副部長が講師を務めた。「歯周治療と補綴治療を一連で行い、歯周病安定期治療(SPT)へと移行する症例」と、「当初は居宅に訪問診療をしていたが、患者の容態の変化により、病院、施設へと訪問先が変更になった症例」の二症例を解説した。参加者からは歯周治療の流れ、歯科衛生士法の解釈などについて質疑が出された。
カルテ記載については、医科歯科それぞれで講習。
医科では小林審査指導対策部員が講師を務めた。カルテの様式および記載の方法、診療報酬の算定要件等で注意が必要な点について説明した。特に医学管理、在宅医療の算定要件の多くに「管理・指導内容の要点を診療録に記載すること」との規定があるため、カルテ記載が特に重要であると強調した。
歯科では金子副部長が講師を務めた。「歯周治療と補綴治療を一連で行い、歯周病安定期治療(SPT)へと移行する症例」と、「当初は居宅に訪問診療をしていたが、患者の容態の変化により、病院、施設へと訪問先が変更になった症例」の二症例を解説した。参加者からは歯周治療の流れ、歯科衛生士法の解釈などについて質疑が出された。