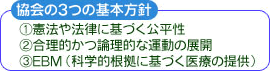論壇
精神科診断の変貌
富士見市 里村 淳
精神科の病気の多くは診断の根拠となるバイオマーカー(生物学的指標)をもたない。バイオマーカーとは、ある疾患の有無、病状の変化や治療の効果の指標となる項目・生体由来のデータであり、血液検査、画像診断、生理学的検査などから得られる生体由来のデータである。いうまでもなく、身体疾患の診断、病状の評価は、これらバイオマーカーが基本となる。それに対し、統合失調症、うつ病、不安障害など、精神科の代表的な疾患は症状と経過から判断するのであり、科学的検証性に乏しい。定型的な病像を呈する場合はよいが、そうでない場合の診断の一致率は低い。精神科の患者の中には、カルテの病名がある時はうつ病、ある時は統合失調症などと、基本となる障害が定まらない事例はめずらしくない。
精神鑑定では、鑑定医によって診断結果が異なることがあり、社会的に注目されている事件では、精神科に疑問をいだく人がいることも確かだ。とくに、うつ病の診断は難物で、医師から見て到底うつには見えなくても、患者がうつと自己診断することが多い。「うつ病とむち打ち症は医者泣かせ」と言われることがある。ドイツの精神医学者の中には、うつ病の症状はあやふやで研究にならないと評した人もいるくらいである。
精神科では症状をただカルテに記述しただけでは患者のこころの中に入って行くことはできないため、患者の病理をどう理解すればよいのかを考えることが精神科医の仕事でもある。つまり、患者の精神や行動の異常をどう理解するか、これを精神病理学という。もちろん科学的検証性などない。精神病理学などは何とでも言える、科学ではない、医学ではないと酷評する人もいるが、患者のこころを理解し関係性を築くためには避けては通れない。とはいえ、精神科医の主観に頼ることになるので、ときには臨床とはまったくかけはなれた哲学的な領域に及ぶこともある。
そこで、精神疾患の診断に統一性をもたせるために、国際的な診断マニュアルが登場した。その代表がアメリカの精神医学会が作成した「精神疾患の診断・統計マニュアルDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM)」である。1952年に第一版が出版され、定期的に改定され現在は第五版DSM-5(2013年)である。また、世界保健機構(WHO)の国際疾病分類 The International Classification of Disorders(ICD)の第5章(F項目)が「精神および行動の障害」となっているが、これはDSMの後を追うようなかたちで編集されており、DSMがアメリカの文化を強く反映しているのに対し、ICDは世界中どこでも使えるよう配慮されている。
わが国では、役所に出す書類の診断名はICDを使用するように義務付けられている。学会の発表ではDSMあるいはICDの診断基準を満たしていると前置きして発表するのが通例となっている。精神科医にとってこれらの国際分類の改定は憲法改定に等しい。しかし、これらの診断基準は操作的診断と言って、精神病理学的な視点を排し、症状だけからなる項目をいくつ以上満たすかというポイント制になっており、臨床の現場では使いにくいと言う評判もあった。しかし、2018年に約30年ぶりに改定されたICD-11は一口で言うと、じつに使いやすいものとなった。そればかりか、ICD-10はDSMの後を追っていたが、2018年の改定では独自性が発揮されるようになり、いっきに実地臨床に即したものになった。
近々、ICD-11の日本語版が発売される予定であるが、これまでとは違いかなり分厚いものとなるようである。しかも内容は臨床現場ですぐ使えるような形になっており、ICD-11があれば教科書は必要ないかもと、編集に係った委員の中には言う人もいる。とくに、正常と異常という区別から、健常者と病気の連続性を重視する視点が取り入れられ、じつに日常臨床にかなったものとなっている。そのほかにも、患者を精神病理学的視点からも診るという、精神科医のアイデンティティーにもかかわるものが復活したことを歓迎している臨床家も多いようである。
精神鑑定では、鑑定医によって診断結果が異なることがあり、社会的に注目されている事件では、精神科に疑問をいだく人がいることも確かだ。とくに、うつ病の診断は難物で、医師から見て到底うつには見えなくても、患者がうつと自己診断することが多い。「うつ病とむち打ち症は医者泣かせ」と言われることがある。ドイツの精神医学者の中には、うつ病の症状はあやふやで研究にならないと評した人もいるくらいである。
精神科では症状をただカルテに記述しただけでは患者のこころの中に入って行くことはできないため、患者の病理をどう理解すればよいのかを考えることが精神科医の仕事でもある。つまり、患者の精神や行動の異常をどう理解するか、これを精神病理学という。もちろん科学的検証性などない。精神病理学などは何とでも言える、科学ではない、医学ではないと酷評する人もいるが、患者のこころを理解し関係性を築くためには避けては通れない。とはいえ、精神科医の主観に頼ることになるので、ときには臨床とはまったくかけはなれた哲学的な領域に及ぶこともある。
そこで、精神疾患の診断に統一性をもたせるために、国際的な診断マニュアルが登場した。その代表がアメリカの精神医学会が作成した「精神疾患の診断・統計マニュアルDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM)」である。1952年に第一版が出版され、定期的に改定され現在は第五版DSM-5(2013年)である。また、世界保健機構(WHO)の国際疾病分類 The International Classification of Disorders(ICD)の第5章(F項目)が「精神および行動の障害」となっているが、これはDSMの後を追うようなかたちで編集されており、DSMがアメリカの文化を強く反映しているのに対し、ICDは世界中どこでも使えるよう配慮されている。
わが国では、役所に出す書類の診断名はICDを使用するように義務付けられている。学会の発表ではDSMあるいはICDの診断基準を満たしていると前置きして発表するのが通例となっている。精神科医にとってこれらの国際分類の改定は憲法改定に等しい。しかし、これらの診断基準は操作的診断と言って、精神病理学的な視点を排し、症状だけからなる項目をいくつ以上満たすかというポイント制になっており、臨床の現場では使いにくいと言う評判もあった。しかし、2018年に約30年ぶりに改定されたICD-11は一口で言うと、じつに使いやすいものとなった。そればかりか、ICD-10はDSMの後を追っていたが、2018年の改定では独自性が発揮されるようになり、いっきに実地臨床に即したものになった。
近々、ICD-11の日本語版が発売される予定であるが、これまでとは違いかなり分厚いものとなるようである。しかも内容は臨床現場ですぐ使えるような形になっており、ICD-11があれば教科書は必要ないかもと、編集に係った委員の中には言う人もいる。とくに、正常と異常という区別から、健常者と病気の連続性を重視する視点が取り入れられ、じつに日常臨床にかなったものとなっている。そのほかにも、患者を精神病理学的視点からも診るという、精神科医のアイデンティティーにもかかわるものが復活したことを歓迎している臨床家も多いようである。