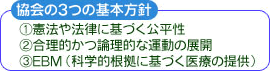【埼玉県保険医協会 理事長談話】
「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い」(6月27日付厚労省事務連絡)発出について
保険証復活こそが、混乱を防ぐ最も確実な方法です
2025年7月2日
埼玉県保険医協会 理事長 渡部 義弘
埼玉県保険医協会 理事長 渡部 義弘
厚労省は、6月27日付けで事務連絡「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱い」を発出しました。埼玉県内の市町村国保をはじめ、全国多数の自治体国保の保険証が7月末に有効期限切れとなる目前のタイミングで、医療機関に対し期限切れの保険証でも資格確認を行い、10割でなく3割(場合によっては2割)を患者から受領するよう求めるものです。
保険証の有効期限切れが多数生じることに伴い、医療機関や自治体の窓口で起きる様々な混乱に対して軽減回避させる方策を厚労省が示したことは評価に値すると考えます。しかしながら、少なくとも5点について指摘せざるを得ません。
さらに言えば、混乱の原因である「保険証廃止」を強行し、「保険証復活」を講じなかった与党らの国会における不作為の責任は極めて重大です。また、本事務連絡の発出をしながら、先の国会審議の中では特段の対応の必要性を認めなかった厚労大臣と厚労省の責任も重大です。
保険証の有効期限切れが多数生じることに伴い、医療機関や自治体の窓口で起きる様々な混乱に対して軽減回避させる方策を厚労省が示したことは評価に値すると考えます。しかしながら、少なくとも5点について指摘せざるを得ません。
さらに言えば、混乱の原因である「保険証廃止」を強行し、「保険証復活」を講じなかった与党らの国会における不作為の責任は極めて重大です。また、本事務連絡の発出をしながら、先の国会審議の中では特段の対応の必要性を認めなかった厚労大臣と厚労省の責任も重大です。
1 医療機関への丸投げによる解決
有効期限が切れた保険証の提示によって保険診療を受診できるというルールは、法令上に存在しません。本事務連絡は超法規的措置を医療機関側に一方的に求め、混乱の軽減回避策としています。
混乱の原因は政治と行政が予見できている事態に真摯に向き合ってこなかったことにあります。資格確認実務を担う開業医からは昨年以前から「保険証は存続」「廃止は時期尚早」の声が多数出されてきました。
多くの混乱発生が懸念されていることは、本会や他県の保険医協会、全国保険医団体連合会から再三に亘り指摘をしてきたところです。6月に閉会した通常国会の中でも野党議員から指摘があったものです。
様々な現場当事者・関係者の要望や声を無視してきた経過のうえに現在があります。この間の後手後手の対処策が、資格確認ツールや説明事項の増加を招き、医療現場における資格確認実務は負担が増え、難儀になっています。
早急に保険証を復活させることが、国民皆保険制度に安定をもたらす確実で簡単な方策です。これ以上、医療現場へ負担をかけることは容認できません。
混乱の原因は政治と行政が予見できている事態に真摯に向き合ってこなかったことにあります。資格確認実務を担う開業医からは昨年以前から「保険証は存続」「廃止は時期尚早」の声が多数出されてきました。
多くの混乱発生が懸念されていることは、本会や他県の保険医協会、全国保険医団体連合会から再三に亘り指摘をしてきたところです。6月に閉会した通常国会の中でも野党議員から指摘があったものです。
様々な現場当事者・関係者の要望や声を無視してきた経過のうえに現在があります。この間の後手後手の対処策が、資格確認ツールや説明事項の増加を招き、医療現場における資格確認実務は負担が増え、難儀になっています。
早急に保険証を復活させることが、国民皆保険制度に安定をもたらす確実で簡単な方策です。これ以上、医療現場へ負担をかけることは容認できません。
2 いまだに周知不足 懸念の払拭に尽力を
混乱が懸念される最大の理由は、国民や患者に、保険証廃止後の資格確認方法や、資格確認書の存在や切替え時期、交付対象や交付方法などがこれまで周知徹底できていないことにあります。そして、有効期限の7月の段階でも、大きく広報がされている様子は見受けられません。積極的に広報をすべきです。
政府の広報はマイナ保険証のPRに重きを置きすぎです。保険証を廃止しておきながら詳細にわたる周知を怠ってきた政府の施策と見通しの悪さに問題があることを指摘せざるを得ません。保険証が60年にわたって全国民に届けられてきた先人の努力に敬意を払わず軽率に廃止を発案した過去の大臣らの不見識さにはさらに大きな問題があることは言うまでもありません。
政府の広報はマイナ保険証のPRに重きを置きすぎです。保険証を廃止しておきながら詳細にわたる周知を怠ってきた政府の施策と見通しの悪さに問題があることを指摘せざるを得ません。保険証が60年にわたって全国民に届けられてきた先人の努力に敬意を払わず軽率に廃止を発案した過去の大臣らの不見識さにはさらに大きな問題があることは言うまでもありません。
3 遅い判断と曖昧な対応 - 国会会期中に判断できなかった問題
本事務連絡が超法規的な内容で、多くの保険証の有効期限が1か月余りという切羽詰まった時期に発出されたことも問題です。また、同様の混乱は国保のみならず協会けんぽや健保組合など社会保険の保険証でも発生することが見込まれます。マイナ保険証の有効期限切れが多数生じることが明らかなのにも関わらず、本事務連絡では適用を国保に限定していることは問題です。
医療機関は保険資格の確認事務について規則に則って忠実に正確に行うことを要請されています。有効期限切れの保険証を暫定的に取り扱うことを要請するならば、その必要性などを国会で審議のうえ決定されるべきです。そうした熟議を経ていない本事務連絡は厚労省から医療機関へのお願い事項にすぎません。
期限切れの保険証の確認は、オンライン資格確認システムによる参照の確実性を前提にしていますがその点は現状では担保されていません。確認ができない場合には患者から10割負担を受領することもあり得るものです。また、「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者を防ぐこともできません。本事務連絡は、曖昧な性格に加えて、問題解決できないものを含んだままです。厚労大臣は国会会期中にしっかりと対応策を示すべきでした。
医療機関は保険資格の確認事務について規則に則って忠実に正確に行うことを要請されています。有効期限切れの保険証を暫定的に取り扱うことを要請するならば、その必要性などを国会で審議のうえ決定されるべきです。そうした熟議を経ていない本事務連絡は厚労省から医療機関へのお願い事項にすぎません。
期限切れの保険証の確認は、オンライン資格確認システムによる参照の確実性を前提にしていますがその点は現状では担保されていません。確認ができない場合には患者から10割負担を受領することもあり得るものです。また、「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者を防ぐこともできません。本事務連絡は、曖昧な性格に加えて、問題解決できないものを含んだままです。厚労大臣は国会会期中にしっかりと対応策を示すべきでした。
4 疑問が残る判断根拠 -「蓋然性なし」から一転
厚労省は、混乱が多発することを見込んで、後期高齢者には、暫定1年間で全員に資格確認書を交付することを4月に発表していましたが、自治体国保については頑なに資格確認書の全員交付を認めませんでした。
5月30日には、わざわざ「後期高齢者のように、(略)マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと言える状況ではなく、(略)全員一律に資格確認書を交付する状況ではないと考えています」と強調し、世田谷区や渋谷区のように資格確認書の全員交付を行う自治体の増加を牽制する事務連絡さえ発出していたものです。
今回の事務連絡では これまでの頑な言質を一転し 「気がつかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者」「健康保険証の切替えに伴って通知された『資格情報のお知らせ』のみを持参する患者」が医療機関を訪れることも当面は想定される、として前述の扱いを示しています。
多くの自治体から意見や声が厚労省に届いているならば、公表のうえ、今回の判断に立ったことを説明すべきではないでしょうか。超法規的措置を示した責任の所在も明示が必要です。
5月30日には、わざわざ「後期高齢者のように、(略)マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと言える状況ではなく、(略)全員一律に資格確認書を交付する状況ではないと考えています」と強調し、世田谷区や渋谷区のように資格確認書の全員交付を行う自治体の増加を牽制する事務連絡さえ発出していたものです。
今回の事務連絡では これまでの頑な言質を一転し 「気がつかずに有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者」「健康保険証の切替えに伴って通知された『資格情報のお知らせ』のみを持参する患者」が医療機関を訪れることも当面は想定される、として前述の扱いを示しています。
多くの自治体から意見や声が厚労省に届いているならば、公表のうえ、今回の判断に立ったことを説明すべきではないでしょうか。超法規的措置を示した責任の所在も明示が必要です。
5 国民皆保険を守るために保険証との併走・併用を
60数年前、皆保険の創設時に国保関係者は、加入者・世帯主から保険料を受領するために、国民皆保険の理念や仕組みを繰り返し説明・説得を試み、年月を要して皆保険制度として成立させてきました。医療機関もルールに則って対応をしてきました。
先人達の開拓とその後の制度の維持に多くの努力がかけられて皆保険制度は定着し発展してきました。しかしながらマイナ保険証の強要政策により制度の根幹である、資格確認の方法が、これほどまでに複雑、不安定になっています。
マイナ保険証は使用したい方が使用し、保険証を使用したい方に保険証を使用することを認め、一定期間「併走」「併用」とすれば、問題は収束します。
政府と与党はこれまでの拙速な進め方と周知不足を認めて、早急に保険証を復活させてください。
先人達の開拓とその後の制度の維持に多くの努力がかけられて皆保険制度は定着し発展してきました。しかしながらマイナ保険証の強要政策により制度の根幹である、資格確認の方法が、これほどまでに複雑、不安定になっています。
マイナ保険証は使用したい方が使用し、保険証を使用したい方に保険証を使用することを認め、一定期間「併走」「併用」とすれば、問題は収束します。
政府と与党はこれまでの拙速な進め方と周知不足を認めて、早急に保険証を復活させてください。
以上