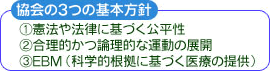論壇
医療制度の崩壊を招く政策転換 国家の優先順位を問い直すとき
川口市 石津 英喜
近年、日本の医療制度は「崩壊の危機」ではなく、すでに一部で崩壊が現実化している。背景には、米国からの防衛費増額要求と、それに呼応する政府の財政再配分の方向転換がある。トランプ政権は日本に対しGDP比3~3.5%の防衛費拡大を迫ったとされ、NATOの防衛費目標引き上げもアジア諸国に圧力をかけている。これに応じるかたちで、日本政府はGDP比2%・43兆円の目標を掲げ、2027年度に向けた防衛費拡大を既定路線とした。その財源確保の一環として、社会保障とりわけ医療費の圧縮が進められている。
財務省は診療報酬の据え置きや後期高齢者の自己負担増を進め、高額療養費制度の見直しにも着手。延期された負担限度額の引き上げは、細かな負担区分導入というかたちで再浮上している。さらに「骨太の方針2025」には、OTC類似薬の保険適用除外、病床削減、地域医療構想の加速など、医療制度を構造的に削減する改革が並ぶ。こうした動きは、制度的脆弱性と急速な人口減少・高齢化という構造問題が交錯する中で、医療提供体制を深刻に蝕んでいる。
実際、多くの医療機関が人件費や物価上昇の波を受けて赤字経営に陥り、特に民間中小病院では倒産・閉鎖が相次いでいる。医師、看護師に加えて薬剤師や技師といったコメディカル職でも人材不足が慢性化し、若年層は給料の良い他の産業にながれ、医療職離れが止まらない。人件費増を吸収できない医療機関は淘汰され「選択と集中」の名のもとで病院統廃合が進み「地域医療の地殻変動」とも言える事態が各地で進行中だ。高齢者や交通弱者が医療へのアクセスを失い、命に関わる格差が現実のものとなりつつある。このような状況下で「国民皆保険」という理念は形骸化しており、地域・世代・制度間での多層的格差が制度の公平性を揺るがしている。国民の中には「なぜ保険料を払い続ける必要があるのか」という疑問すら広がっており、制度の持続可能性は財政以前の問題に直面している。
本論壇が紙面に出るころには参議院選挙の結果がでていると思うが、社会保障費の削減を掲げている各党の議員数はどうなっているだろうか?
医療費抑制の名目で予防や初期対応を縮小すれば、重症化による高額治療が増え、結果として財政負担は膨らむ。高齢化社会で医療を削ることは「未然に防ぐ力」を手放すことであり、長期的には国全体の生産性・持続可能性を損なう。地方病院の統廃合や診療科の削減は、都市部と地方の格差が広がるばかりか「住んでいる場所によって命の価値が変わる」状況を招きかねない。医療は「コスト」ではなく「社会的投資」であるという原点に立ち返り、現場の声を反映した政策が不可欠だ。これ以上診療報酬が据え置かれれば、赤字解消のため自由診療・混合診療を優先とするような医療機関も多く出現するのではないかの懸念がある。「医療費削減=医療格差拡大」となるだろう。実際のところ、政府は混合診療を段階的に容認・拡充する方向にあり、保険外負担が増えることで、経済力によって受けられる医療に差がでる可能性もある。
日本の誇る「国民皆保険」は、保険証1枚ですべての人に医療アクセスを保障する世界に誇れる制度である。今こそ、この国の優先順位を問い直すべきときだ。防衛や経済成長がいかに重要であっても、国民の命と健康を犠牲にすることが許されてはならない。
財務省は診療報酬の据え置きや後期高齢者の自己負担増を進め、高額療養費制度の見直しにも着手。延期された負担限度額の引き上げは、細かな負担区分導入というかたちで再浮上している。さらに「骨太の方針2025」には、OTC類似薬の保険適用除外、病床削減、地域医療構想の加速など、医療制度を構造的に削減する改革が並ぶ。こうした動きは、制度的脆弱性と急速な人口減少・高齢化という構造問題が交錯する中で、医療提供体制を深刻に蝕んでいる。
実際、多くの医療機関が人件費や物価上昇の波を受けて赤字経営に陥り、特に民間中小病院では倒産・閉鎖が相次いでいる。医師、看護師に加えて薬剤師や技師といったコメディカル職でも人材不足が慢性化し、若年層は給料の良い他の産業にながれ、医療職離れが止まらない。人件費増を吸収できない医療機関は淘汰され「選択と集中」の名のもとで病院統廃合が進み「地域医療の地殻変動」とも言える事態が各地で進行中だ。高齢者や交通弱者が医療へのアクセスを失い、命に関わる格差が現実のものとなりつつある。このような状況下で「国民皆保険」という理念は形骸化しており、地域・世代・制度間での多層的格差が制度の公平性を揺るがしている。国民の中には「なぜ保険料を払い続ける必要があるのか」という疑問すら広がっており、制度の持続可能性は財政以前の問題に直面している。
本論壇が紙面に出るころには参議院選挙の結果がでていると思うが、社会保障費の削減を掲げている各党の議員数はどうなっているだろうか?
医療費抑制の名目で予防や初期対応を縮小すれば、重症化による高額治療が増え、結果として財政負担は膨らむ。高齢化社会で医療を削ることは「未然に防ぐ力」を手放すことであり、長期的には国全体の生産性・持続可能性を損なう。地方病院の統廃合や診療科の削減は、都市部と地方の格差が広がるばかりか「住んでいる場所によって命の価値が変わる」状況を招きかねない。医療は「コスト」ではなく「社会的投資」であるという原点に立ち返り、現場の声を反映した政策が不可欠だ。これ以上診療報酬が据え置かれれば、赤字解消のため自由診療・混合診療を優先とするような医療機関も多く出現するのではないかの懸念がある。「医療費削減=医療格差拡大」となるだろう。実際のところ、政府は混合診療を段階的に容認・拡充する方向にあり、保険外負担が増えることで、経済力によって受けられる医療に差がでる可能性もある。
日本の誇る「国民皆保険」は、保険証1枚ですべての人に医療アクセスを保障する世界に誇れる制度である。今こそ、この国の優先順位を問い直すべきときだ。防衛や経済成長がいかに重要であっても、国民の命と健康を犠牲にすることが許されてはならない。