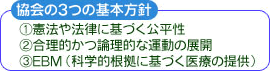論壇
開業10年 歯科医療における変化を考察する
久喜市 渋谷 由之
日本の歯科診療報酬制度は、国民皆保険制度のもとで医療の質と公平性を担保する重要な仕組みである。診療報酬は2年ごとに改定され、医療技術の進歩や社会情勢に応じて点数が見直されてきた。2015年以降、歯科診療報酬は微増傾向にあり、2024年の改定では「ベースアップ評価料」や「医療DX推進加算」などが新設された。特に注目すべきは、歯科外来・在宅ベースアップ評価料で、初診時に10点、再診時に2点が加算される仕組みが導入されたことである。
歯科診療報酬の中でも基本的な項目である初診料と再診料の推移を見ると、2015年時点では初診料が234点、再診料が48点であったのに対し、2025年には初診料が264点、再診料が56点へとそれぞれ増加している。この10年間で初診料は約13%、再診料は約17%の上昇となっており、物価上昇率とほぼ同程度の伸びであるが、材料費や人件費の高騰を考慮すると、診療報酬の実質的な価値はむしろ低下しているといえる。物価高騰の影響は大きい。
2015年から2025年にかけて、日本の消費者物価指数(CPI)は約13%上昇し、特に2022年以降のインフレ傾向は顕著である。歯科材料の多くは輸入品であり、金銀パラジウム合金(金パラ)やセラミックなどの価格は過去最高水準を更新し続けている。保険診療であっても歯科医院の負担が増加している。
さらに、人件費の高騰も歯科医療現場に深刻な影響を与えている。歯科衛生士や歯科技工士の人材確保が困難になっており、都市部では歯科衛生士の平均年収が400万円を超える。「働き方改革」の名の下、長時間労働の是正や有給取得の義務化が進み、歯科医院の運営体制にも変化が求められている。スタッフの定着率向上や研修制度の整備も重要な課題となっており、経営者としての視点が歯科医師に強く求められるようになっている。
社会的背景としては、2025年には団塊の世代がすべて75歳以上となり、後期高齢者人口が急増する。在宅歯科医療や訪問診療の需要が高まる一方で、通院困難な高齢者への対応体制が十分に整っていないという課題も浮き彫りになっている。また、歯科医院の後継者不足も深刻であり、60代以上の歯科医師が多くを占める中、後継者が不在のまま閉院するケースが増加している。地域医療の空白地帯が生まれつつある現状は、医療制度の持続可能性に対する警鐘でもある。
このような状況に対応するためには、診療報酬の柔軟な見直しとともに、地域医療の実情に即した運用、そして歯科医療従事者の働きやすい環境整備が求められる。歯科医療は単なる治療にとどまらず、全身の健康や生活の質に直結する重要な分野である。社会全体でその価値を再認識し、持続可能な制度設計と支援体制の構築が急務となっている。
2025年現在、勤務歯科医師の平均年収は約690万円、一方、東証プライム上場企業社員の平均年収は735万円である。福利厚生等考慮すると安定性では上場企業が優位とも言える。また開業時に要する費用として、建築坪単価は一年前と比較し二倍程度、初期導入機材費も1.5倍から2倍に増加し、スタッフの賃金上昇も著しい。坪単価が60万円から120万円に、初期導入器材費が3,000万から6,000万円に上昇しており、高度な最新設備導入(歯科で言う三種の神器、CT、マイクロスコープ、口腔内スキャナー)も必要不可欠になっている。
色々なことを書いてきたが10年でここまで変化があったということに正直驚いている。これに加えマイナンバーカードと保険証の一体化なども始まった。10年後どうなっているか。医療者にも患者にもわかりやすく、簡便に医療が受けられるようにしたい。
歯科診療報酬の中でも基本的な項目である初診料と再診料の推移を見ると、2015年時点では初診料が234点、再診料が48点であったのに対し、2025年には初診料が264点、再診料が56点へとそれぞれ増加している。この10年間で初診料は約13%、再診料は約17%の上昇となっており、物価上昇率とほぼ同程度の伸びであるが、材料費や人件費の高騰を考慮すると、診療報酬の実質的な価値はむしろ低下しているといえる。物価高騰の影響は大きい。
2015年から2025年にかけて、日本の消費者物価指数(CPI)は約13%上昇し、特に2022年以降のインフレ傾向は顕著である。歯科材料の多くは輸入品であり、金銀パラジウム合金(金パラ)やセラミックなどの価格は過去最高水準を更新し続けている。保険診療であっても歯科医院の負担が増加している。
さらに、人件費の高騰も歯科医療現場に深刻な影響を与えている。歯科衛生士や歯科技工士の人材確保が困難になっており、都市部では歯科衛生士の平均年収が400万円を超える。「働き方改革」の名の下、長時間労働の是正や有給取得の義務化が進み、歯科医院の運営体制にも変化が求められている。スタッフの定着率向上や研修制度の整備も重要な課題となっており、経営者としての視点が歯科医師に強く求められるようになっている。
社会的背景としては、2025年には団塊の世代がすべて75歳以上となり、後期高齢者人口が急増する。在宅歯科医療や訪問診療の需要が高まる一方で、通院困難な高齢者への対応体制が十分に整っていないという課題も浮き彫りになっている。また、歯科医院の後継者不足も深刻であり、60代以上の歯科医師が多くを占める中、後継者が不在のまま閉院するケースが増加している。地域医療の空白地帯が生まれつつある現状は、医療制度の持続可能性に対する警鐘でもある。
このような状況に対応するためには、診療報酬の柔軟な見直しとともに、地域医療の実情に即した運用、そして歯科医療従事者の働きやすい環境整備が求められる。歯科医療は単なる治療にとどまらず、全身の健康や生活の質に直結する重要な分野である。社会全体でその価値を再認識し、持続可能な制度設計と支援体制の構築が急務となっている。
2025年現在、勤務歯科医師の平均年収は約690万円、一方、東証プライム上場企業社員の平均年収は735万円である。福利厚生等考慮すると安定性では上場企業が優位とも言える。また開業時に要する費用として、建築坪単価は一年前と比較し二倍程度、初期導入機材費も1.5倍から2倍に増加し、スタッフの賃金上昇も著しい。坪単価が60万円から120万円に、初期導入器材費が3,000万から6,000万円に上昇しており、高度な最新設備導入(歯科で言う三種の神器、CT、マイクロスコープ、口腔内スキャナー)も必要不可欠になっている。
色々なことを書いてきたが10年でここまで変化があったということに正直驚いている。これに加えマイナンバーカードと保険証の一体化なども始まった。10年後どうなっているか。医療者にも患者にもわかりやすく、簡便に医療が受けられるようにしたい。