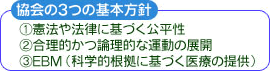論壇
少子高齢化、労働力不足、そして外国人問題
富士見市 里村 淳
わが国は今日、少子高齢化、労働力不足、外国人問題で揺れている。これは日本に限ったことではなく、ヨーロッパ諸国ではとうの昔に始まっている。とくにドイツでは顕著である。最近、私の友人があるドイツ人から、「日本も気を付けたほうが良い。いずれ日本もそうなる」と忠告されたという。
現在、ドイツは人口の約3割を移民が占め、社会保障に関する財政負担が500億ユーロ(7兆8,000億円)に達した。2015年と16年にやってきた120万人以上の難民を心よく受け入れたことが大きい。これは人道支援だけではなく、労働力の不足を補うという意味もあったらしい。シリアからの難民は都市部に集中しており、小・中学校ではドイツ語のわからない難民の子供が多くて授業にならないという。また、凶悪犯罪が増えたこともよく知られている。しかし、大量の難民発生はヨーロッパに限ったことではない。わが国でも近隣に、いわゆる「有事」が発生して大量の難民が押し寄せて来る可能性は否定できない。
日本とドイツは歴史的な共通性からよく比較されるが、労働力不足とその対策はドイツの方が大先輩なのだ。戦後の復興期、ドイツは早くも労働力不足が生じ、1955年、それを補うためにトルコ、旧東欧諸国などから外国人労働者を導入することになった。戦争によるドイツの軍人・民間の人的被害は日本の2倍以上であり、それが戦後の復興の人手不足につながった要因の一つとも言える。
私は今から約50年前、つまり1975年から77年まで、ドイツのマインツ大学病院に留学の経験がある。そのころ「Gastarbeiter(外国人労働者あるいは移民労働者)」がドイツ社会を理解するためのひとつのキーワードになっていた。病院のリネン室に行くと全員がトルコ人女性、病棟の看護師は師長と主任クラスがドイツ人であとは外国人、病棟の掃除婦はスペイン人といった具合で、病院だけでなく社会全体が底辺の人材をガスト・アルバイターに頼っていた。当時、わが国の労働状況を見ると、上も下もすべて自国民だけでやっているのが普通だったが、外から見るとやや異様な感じがした。
今年になって久しぶりにドイツを訪れる機会があったが、街中でヒジャブを被った女性がじつに多かった。タクシーの運転手はほとんど外国人のような印象だった。タクシーに乗って行く先を告げても、複雑な地名はお客自身がカーナビに入力するよう頼まれた。わが国でも最近は外国人の労働者を街中で見かけることが多くなったが、ドイツのことを考えるとこれはまだ序の口と言ってよい。
ドイツは戦時中の負の遺産を今でも背負い続けており、難民に対する人道支援には前向きにならざるを得ないという事情があるが、国民の財政負担、治安の悪化などから、左派政権までが移民政策に対してやや強硬になってきた。さらに、移民排斥を主張する右派ポピュリズム政党「AfD(Alternative fuer Deutschland ドイツのための選択肢)」は2025年2月の総選挙で前回より10.4ポイント増の20.8%の票を獲得して野党第一党にのし上がった。これに危機感を覚えるドイツ人は少なくない。
近年わが国では福祉サービス目当ての入国や、難民と偽って出稼ぎ目的の外国人が増えて国民の不満が高まって来たせいか、今夏の参議院選挙では外国人問題を掲げる政党が支持を集めた。その結果、世論はインバウンドの増加による弊害も加わって外国人問題に対して過敏になりつつある。わが国では労働力不足を補う意味で1993年、「外国人技能実習制度」が創設された。しかし、劣悪な労働環境から失踪する者が続出したこともあり、2027年に廃止となり「育成就労制度」に変更されることになった。わが国の人手不足に対する国の対応は長期的な視野に立ったものではなく実に姑息と、評判が悪い。
少子化による労働力不足はこれからさらに進むことが予測される。ロボットやAIでその不足を補うという意見もあるが、まず、国民が世界の労働事情をよく理解し、その上で外国人労働者の受け入れの法整備を進めることも大切である。一方、行き過ぎた人道主義は国の財政を圧迫する。先のドイツ人の忠告が気になる。
現在、ドイツは人口の約3割を移民が占め、社会保障に関する財政負担が500億ユーロ(7兆8,000億円)に達した。2015年と16年にやってきた120万人以上の難民を心よく受け入れたことが大きい。これは人道支援だけではなく、労働力の不足を補うという意味もあったらしい。シリアからの難民は都市部に集中しており、小・中学校ではドイツ語のわからない難民の子供が多くて授業にならないという。また、凶悪犯罪が増えたこともよく知られている。しかし、大量の難民発生はヨーロッパに限ったことではない。わが国でも近隣に、いわゆる「有事」が発生して大量の難民が押し寄せて来る可能性は否定できない。
日本とドイツは歴史的な共通性からよく比較されるが、労働力不足とその対策はドイツの方が大先輩なのだ。戦後の復興期、ドイツは早くも労働力不足が生じ、1955年、それを補うためにトルコ、旧東欧諸国などから外国人労働者を導入することになった。戦争によるドイツの軍人・民間の人的被害は日本の2倍以上であり、それが戦後の復興の人手不足につながった要因の一つとも言える。
私は今から約50年前、つまり1975年から77年まで、ドイツのマインツ大学病院に留学の経験がある。そのころ「Gastarbeiter(外国人労働者あるいは移民労働者)」がドイツ社会を理解するためのひとつのキーワードになっていた。病院のリネン室に行くと全員がトルコ人女性、病棟の看護師は師長と主任クラスがドイツ人であとは外国人、病棟の掃除婦はスペイン人といった具合で、病院だけでなく社会全体が底辺の人材をガスト・アルバイターに頼っていた。当時、わが国の労働状況を見ると、上も下もすべて自国民だけでやっているのが普通だったが、外から見るとやや異様な感じがした。
今年になって久しぶりにドイツを訪れる機会があったが、街中でヒジャブを被った女性がじつに多かった。タクシーの運転手はほとんど外国人のような印象だった。タクシーに乗って行く先を告げても、複雑な地名はお客自身がカーナビに入力するよう頼まれた。わが国でも最近は外国人の労働者を街中で見かけることが多くなったが、ドイツのことを考えるとこれはまだ序の口と言ってよい。
ドイツは戦時中の負の遺産を今でも背負い続けており、難民に対する人道支援には前向きにならざるを得ないという事情があるが、国民の財政負担、治安の悪化などから、左派政権までが移民政策に対してやや強硬になってきた。さらに、移民排斥を主張する右派ポピュリズム政党「AfD(Alternative fuer Deutschland ドイツのための選択肢)」は2025年2月の総選挙で前回より10.4ポイント増の20.8%の票を獲得して野党第一党にのし上がった。これに危機感を覚えるドイツ人は少なくない。
近年わが国では福祉サービス目当ての入国や、難民と偽って出稼ぎ目的の外国人が増えて国民の不満が高まって来たせいか、今夏の参議院選挙では外国人問題を掲げる政党が支持を集めた。その結果、世論はインバウンドの増加による弊害も加わって外国人問題に対して過敏になりつつある。わが国では労働力不足を補う意味で1993年、「外国人技能実習制度」が創設された。しかし、劣悪な労働環境から失踪する者が続出したこともあり、2027年に廃止となり「育成就労制度」に変更されることになった。わが国の人手不足に対する国の対応は長期的な視野に立ったものではなく実に姑息と、評判が悪い。
少子化による労働力不足はこれからさらに進むことが予測される。ロボットやAIでその不足を補うという意見もあるが、まず、国民が世界の労働事情をよく理解し、その上で外国人労働者の受け入れの法整備を進めることも大切である。一方、行き過ぎた人道主義は国の財政を圧迫する。先のドイツ人の忠告が気になる。